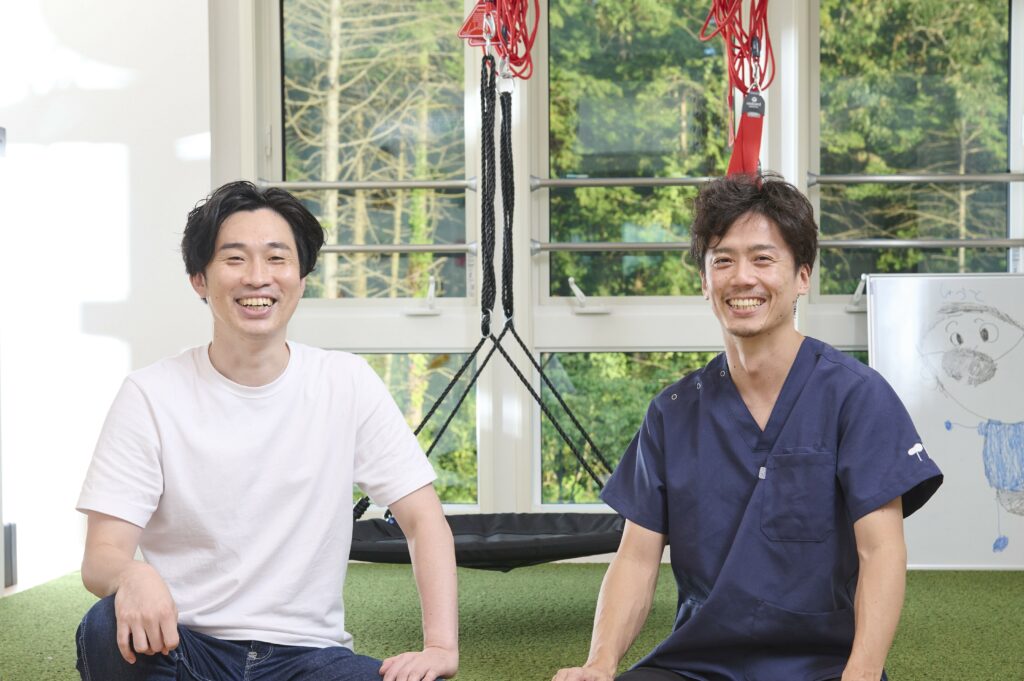地域の医療機関同士が、それぞれの機能や専門性を活かして連携を図る「地域医療連携」。その重要性は、昨今ますます高まっています。患者さんが継続的で適切な医療を受けられることはもちろん、病院経営においても、生き残りをかけた事業戦略の要となります。
早期から、DXを活用した地域医療連携に取り組んできた「恵寿総合病院」理事長・神野正博さん、そして、ネットワーク構築や運用を先導してきた理事長補佐・神野正隆さんに、そのプロセスや課題・障壁の乗り越え方、また、院内外での成果や影響についてお話を伺いました。
2つのセンターを開設。法人全体フローの見える化と最適化を目指す
──恵寿総合病院では、将来にわたって地域から必要とされる存在であるべく、30年以上前から法人グループ内の医療・介護・福祉をつなげるサービス「けいじゅヘルスケアシステム」を提供しています。常に先見性ある取り組みに着手し続ける貴院が、現在、地域医療連携において推し進めていることについて教えてください。

神野理事長 病院での医療が真ん中にあるとするなら、その前には予防や健康管理があり、後には経過観察や介護、そして生活の場があります。「けいじゅヘルスケアシステム」は、これらの統合を図るシステムです。
さらに患者さんは、医療・介護・生活の場における支援を一方向に進むだけでなく、ぐるぐると回っています。病院で治療を受ければそれでおしまい、というケースばかりではありませんから。このサイクルの流れ全体をカバーし、かつスムーズに循環させる仕組み「エコシステム」が必要だと考え、現在もその構築に取り組んでいます。
わかりやすい日本語で言えば「囲い込み」ですね。
しかしこれは、ネガティブな意味ではありません。「我々は、あなたのことをよくわかっていますよ」というメッセージと共に伝え、患者さんが「囲い込まれることが楽だ、安心だ」と思っていただくような仕組みであることが大事です。
当院がしっかりと管理できる仕組みにすれば、少子高齢化により患者さんの母数が減っても、我々の役割や求められる機会が減ることはおそらくないでしょう。
神野理事長補佐 スムーズな流れの構築がいかに大事かということは、PFM(Patient Flow Management:患者フローマネジメント)というワードが非常に重要視されはじめていることからもわかります。
我々は入院前から退院後までの流れを最適化するため、2022年に「入退院管理センター」を立ち上げました。入院早期から、あるいは予定入院患者さんには入院前から関わり、退院・転院後までを見据えて診療の流れを一元管理する部署です。あらゆる指標をリアルタイムでモニタリングし、現在は、院内のベッドコントロールをはじめ、法人内の介護施設の入退室状況や稼働状況も把握して、客観的指標をもとに全体最適での連携調整を行っています。
第1段階として着手した、恵寿総合病院内でのコントロールがうまくいったため、第2段階として、介護施設や福祉施設など法人全体のフロー最適化を図りました。そして今は、第3段階。在宅領域でのフローマネジメントまで一元的に管理し、カバーするべく、2025年4月に「地域包括ケアセンター」を立ち上げ、これまであった訪問診療、訪問看護、訪問介護、訪問リハビリテーション、ケアマネジャーの部署を、在宅系サービスの部署としてひとつにまとめました。
チーム医療が大事だと言われますが、医療・介護の現場は医師、看護師、介護士、薬剤師、セラピストなど、多くの専門職が関わるため、どうしても縦割りになりがちです。そこで、院内の多職種連携はもちろんですが、在宅系サービスにおいても、どのタイミングでどの専門職が介入することが患者さんにとって最適かを、「地域包括ケアセンター」が見える化して一元管理することに着手しています。さらに、訪問スケジュールをAIで管理することで、非常に効率的な訪問が可能になり、ケア時間の確保や質向上にもつながっています。

入退院に関わるさまざまなデータを一元管理している入退院管理センター
地域の他病院とも連携し、患者さんをストレスなく循環させたい
──わずか4年の間に、2つのセンターを開設されたのですね。開設の前後で、どんな変化が見られましたか。
神野理事長補佐 「入退院管理センター」開設を機に、患者さんの紹介を受けるなど地域連携を担う部署もセンター内に移しました。PFMにおいて重要な入口を担当する部署であり、また患者さんを紹介してもらうと同時に、回復後には患者さんを地域にお返しする「逆紹介」にも力を入れていくことが狙いです。
紹介を受けた患者さんを治療し、回復したら地域に戻す。この循環をスムーズに回していき、地域全体で患者さんをサポートする仕組みを整えたかったのです。
神野理事長 治療を終えた患者さんは地域にお戻ししつつも、再び治療が必要になった際には必ず我々が面倒を見る、という仕組みを構築しています。
神野理事長補佐 ここ5年で、紹介数は30%、逆紹介数は90%ほど増えています。紹介率は90%台で、初診患者さん(救急・健診・時間外除く)の内、他の医療機関からの紹介状を持参した方が約9割ということになります。また、当院から別の医療機関へ紹介した患者さんの割合を示す逆紹介率は110%ほどあり、我々が地域連携に非常に注力していることのあらわれだと言えるでしょう。
──紹介された患者さんより、他院へ紹介した患者さんの方が多いということですね。
神野理事長補佐 数字としてはおっしゃる通りですが、逆紹介する際、患者さんが、病院から見放されたと感じてほしくはありません。そのために取り入れているのが、「2人主治医制」です。地域のかかりつけ医にかかりながら、専門治療が必要な際は当院が責任を持って担うなど、連携医と当院が情報を密に共有し、協力してカバーする体制を整えています。この安心感や信頼感が、逆紹介の増加につながった理由のひとつだと思います。
多職種が同等に関わるチーム医療が、スタッフのプロ意識と連携を高める
──「入退院管理センター」そして「地域包括ケアセンター」には、様々な職種の方が関わっていると思いますが、スムーズな業務のためには綿密な相談や連携が不可欠です。
神野理事長補佐 そうですね。「入退院管理センター」の職員は、地域連携課は事務、入退院支援課は看護師、医療福祉相談課はメディカルソーシャルワーカー(以下MSW)、そしてベッドコントロールを担うコマンダーはセンター長である私と2人の副センター長(看護師・MSW)ですので、それぞれ職種が異なります。
神野理事長 「地域包括ケアセンター」にも、看護師や介護士、理学療法士や作業療法士、ケアマネージャーそして医師など多岐にわたる専門職がいますが、当院では看護師は看護のスペシャリストとして、介護士は介護のスペシャリストとして患者さんに関わります。看護は療養の世話を、介護は生活の世話を専門的に担い、それぞれがプロとしての自覚を持ち、独立した同等の立場だという意識を大切にしています。
神野理事長補佐 また院内では、病棟内を小さな集団(セル)に分けて、各セルを何人かの看護師と介護士とリハビリ療法士がセットになり担当する多職種協働のセルケア方式「恵寿セルケアチーム」を編成しています。基本的にスタッフは都度、スタッフステーションに戻るのではなく、常にセル、つまり担当する患者さんのすぐそばにいます。セル内では多職種が自然と連携し、さらに薬剤師や栄養士、MSWらは複数のセルに横断的に関わります。
神野理事長 私たちは誰がどの仕事を受け持つかを、慣習や立場などで決めつけることはありません。厚生労働省の「看護必要度」をひとつの指標とし、セル内の職員が話し合い、また患者さんの状態を考慮して看護と介護の関与度から、受け持ちを決めます。恵寿セルケアチームが無理なく行えているのも、患者さんの状態を仕事分担の指標とすることで、横割りの意識が浸透しているからだと言えるでしょう。
属人化しやすい退院調整も一元管理し、在院日数を着実に短縮
──在院日数の短縮化について、「入退院管理センター」での成果を教えてください。

神野理事長補佐 退院調整は属人化の度合いが高く、医師の方針や担当看護師やMSWの関与度合いなどによって、退院させるタイミングは大きく異なります。この属人化からの脱却も、「入退院管理センター」設立の狙いのひとつでした。そこで、退院調整に関する責任と権限をすべて移譲し、ルールを決めて、センターで一元管理することにしました。
また、退院調整は患者さんの状態が十分に落ち着いてから…と考えていると、治療が終わってから退院待ちの時間が増えかねません。在院日数を適切に短くするためには、入院初期から介入していくことが大事です。「入退院管理センター」で介入のタイミングを見える化・管理することで、属人化の場合はどうしても生じてしまう抜け漏れがなくなりました。
結果的に、在院日数の短縮に大いに役立っています。患者さん目線で最適な医療を最適な期間で提供し、退院後の生活も入院初期から視野に入れ調整をしていきます。またプラスアルファの効果として、診療報酬加算の漏れ防止にもつながっています。
──在院日数の短さなど様々な面での満足度の高さが、紹介率や逆紹介率の向上につながっているのですね。
神野理事長補佐 在院日数を短くし、次の患者さんをすみやかに受け入れる。DXを活用した成果が数値としてもあらわれており、地域連携の先生方からの信頼を得ることにつながっていると感じます。
退院時サマリー作成の自動化やデジタル機器の積極的活用で、残業時間を大幅に削減
──「入退院管理センター」の始動は、スタッフのみなさんの残業時間短縮にも貢献しているのではないかと思います。他に、DXを残業時間削減につなげている好例はありますか?
神野理事長 サマリー作成に、生成AIを活用しています。
電子カルテの中に生成AIを組み込んでおり、これまで2時間程度かかっていた急性期から回復期リハビリまでの最長6カ月以上の患者さんのサマリーでも、およそ5分で完成させることができます。
神野理事長補佐 サマリーは、患者さんの治療や看護に直接関係するものではないものの、医師や看護師にとって、治療経過をまとめる重要な仕事の一つです。しかし作成することが結構な負荷となっていることが少なくありません。実際、毎年当院で実施している看護師の業務量調査からも、サマリー作成をはじめとする時間外の記録業務が多いことが明らかになりました。業務時間内は忙しく記録業務が充分にできず、残業して記録をしてから帰る、というのが実状だったのです。
神野理事長 そこで、生成AIを活用したところ、勤務時間内に記録業務を終わらせることができるようになりました。ボタンを押せば電子カルテの情報に基づいてサマリーが作成されるので、実に簡単です。
神野理事長補佐 生成AIが電子カルテ内から情報を引っ張ってくるので、元となるカルテ記事の精度が高いほど、サマリーの精度も高くなります。医師はカルテの記載がシンプルな場合も多いですが、そんな時には、看護師や薬剤師やMSWなど他の職種のカルテから情報を補い、サマリーを完成させることができます。
──残業時間削減において、生成AIによるサマリー作成の貢献度は高いですか?
神野理事長 そう思います。今、当院のほとんどの看護師は残業をしていません。
神野理事長補佐 医師以外の全職種の平均残業時間は、1ヶ月間で計1時間程度です。また、医師も平均20時間程度と、国が定める残業規定の上限を大きく下回っています。もちろんこれは、サマリー作成の時間短縮だけが要因というわけではありません。DXの推進に加え、多職種連携とタスクシフト・シェアにより、各職種が“その職種にしかできないこと”に集中できる環境が構築されていることも大きいと思います。
神野理事長 例えば、当院では職員全員がスマートフォン(iPhone)を持っており、チャットツール(Microsoft Teams)を介してやりとりしています。
神野理事長補佐 業務用iPhoneにはモバイル電子カルテが搭載されており、患者さんのことはその中のトーク(チャット)で、それ以外の施設内・部署内や委員会、プロジェクトのやりとりはTeamsのチャットですべてやりとりし、皆で情報共有をしています。緊急時以外は基本的にはチャットツールを使うので、各自の都合に合わせてメッセージを送ったり確認したりすることができます。気遣いしすぎることがなく、心理的安全性が保たれ、ストレス軽減にもつながっています。
他にも、議事録の作成もほぼAIに任せています。AIが録音内容を文字起こしして、それを要約して議事録を作成するので、あとは最終チェックをしてMicrosoft Teams内で共有するだけ。それまでは1時間ほどかかっていた作業がほんの数分で終わるので、その分、本来の業務に集中することができます。

──AIへのタスクシフトをうまく活用されていますね。様々な取り組みを通じて、残業時間削減につながった好例だと感じました。
クリニカルパス利用率は約99%。業務効率を高める策はおそれず導入
──結果的に業務改善につながった、という取り組みはありますか?
神野理事長補佐 他にも例えば、2024年に設立した「データセンター」も業務改善につながる大きな力になっています。ここは、法人内のあらゆるデータを可視化して、全職員がそれをいつでも誰でも見られるようにして、利活用することを目的としています。つまり、自分たちの業務がどんな数値やデータとなっているかが可視化され、客観視することができるため、改善ポイントを認識しやすいのです。
──あらゆるものがデータ化されるということは、例えば、このクリニカルパスを用いれば医療費が削減できる、といった分析も効率的にできそうです。
神野理事長補佐 全国約1,000の病院のデータをベンチマーク分析し、全国標準を把握して、当院独自のクリニカルパスに落とし込んでいっています。そこへさらに、患者さんごとの状況を加味し、オーダーメイド化できるようにしています。
患者さんには個別性があるためパスによる標準化はできない、という考えもありますが、標準化があった上で個別化がなされるべきでしょう。そうでなくては、ここでも医師によって指示が異なるという属人化が起きてしまう。ベースとなるのは、医師の好みや傾向を排除した標準化されたクリニカルパス。その上に、患者さんの個別性や医師のこだわりを加えていきます。当院のパスの利用率は約99%。おそらく、全国で一番高いのではないでしょうか。
──クリニカルパスの標準化も、業務軽減につながりますか?
神野理事長補佐 はい。該当するパスを医師が選べば指示が自動で表示されるため、指示をひとつずつ入れる必要がありません。また医師以外の多職種の指示も同時に入ります。取り組みを始めた当初は、数人で夜な夜なパスを作ったので結構大変でしたが、その甲斐あって、今は300ほどのクリニカルパスが蓄積できており、日々ブラッシュアップもしています。
神野理事長 この取り組みがプラスに作用するのは、医師の業務軽減という側面だけではありません。看護師についても、標準化が当たり前になっていれば、逸脱したケースの早期発見につながるでしょう。
このように、当院では多方面で自動化を取り入れ、DXを推し進めています。入院時はパスを使って指示を迅速・適切に出すことができ、退院時はボタンを押せばサマリーが完成する。結果、本来の医療に集中する時間を確保することができます。
他職種や地域との連携もDXにより促進されるため、今後ますます、それぞれの専門職が、自分の専門領域に特化した業務に向き合うことができるようになるでしょう。