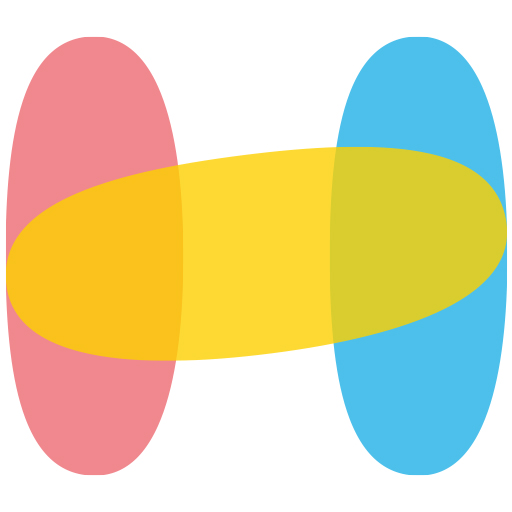新型コロナウイルス感染症のパンデミックで、「看護師」を含むエッセンシャルワーカーの地位向上のための動きが世界中で進んでいます。
看護師の仕事は、「患者に寄り添う」こと。ここだけを聞くと、誰もが家族や友人にしている、普段の生活で実践できることのように感じるかもしれません。
しかし、未知の病気との戦いに苦しみベッドに横たわる患者を数百人単位で抱える病院において、「患者に寄り添う」ケアを行き届かせることは簡単ではありません。看護師は、どのように患者と向き合い、治療を行っていくべきなのでしょうか。
独立行政法人 地域医療機能推進機構(JCHO)大阪病院で新病院設立を設計段階から指揮した、元看護部長の田中小百合さんにインタビューを実施。前編の記事では、看護師が患者さんに「寄り添う」療養環境の考案や、その効果についてお聞きしました。
今回の後編記事では、病院という箱ではなく、そこで働く看護師たちが自分たちでルールを決めて運用していく過程を、組織文化やマネジメント、教育体制の確立といった観点から深堀りしていきます。
医師とナースはクルマの両輪
── 前回の記事では、田中さんが看護師の立場から新病院の設計に携わった経緯についてお伺いしました。この機会が生まれるキッカケとなった、JCHO大阪病院の文化や背景について改めて詳しく教えてください。
JCHO大阪病院の特徴は、職種間の垣根が低いことです。開院当時から患者さんの望む医療に応えるためには、必要性に応じていろいろな職種がチームワークを組んで協力して支えていくことを、当たり前のものとして実践していました。
私が印象的だったのは、JCHO大阪病院に入職するときに言われた「医師とナースはクルマの両輪です」という言葉です。
医師が治療方針を決定し、治療の医療行為を実践する役割を担うのに対して、看護師は医師の方針に従って診療の補助や、治療を受ける患者さんの療養上の世話を担当します。この時に大切になるのが、治療を受ける人として患者さんを観察する能力です。
患者さんの小さな変化を察知し、それが治療による副作用なのか、症状の悪化なのか、病気を受け入れられないことによる不安なのか、家族関係や経済的な気がかりからくる落ち込みなのかなどを観察し、治療を効果的に進めるために必要な情報を医師に提供します。
── まさに治療を進めるうえで二人三脚になる、対等なパートナーということですね。
その通りです。どんなに高価で効果的な治療薬があっても、どんなに医師の手術手技が素晴らしくても、回復過程において小さな変化を見逃してしまうと対処が遅れて効果が出ません。また、治療を受けるうえで直面する痛み・不快・不安・気がかりなどをケアして尊厳を守らなければ、安心して治療を受けられる医療を提供できないのです。
看護師はこのような関わりを24時間継続して行っています。だから、医師とは「両輪」の関係なのです。こうした看護師の役割を尊重する文化があったからこそ、JCHO大阪病院は看護師に新病院建設を協力させてくれたと思います。
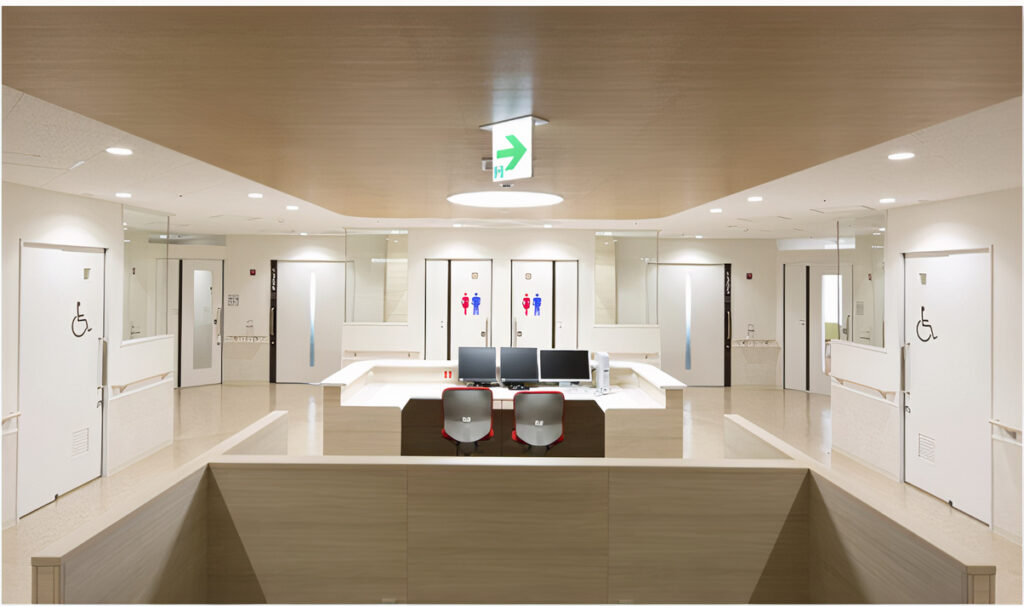
「寄り添い」とケア
── 看護師の仕事は、療養上の世話を通して患者さんに寄り添い尊厳を守ること。それは近年の「エッセンシャルワーカー」の話につながる、重要な観点だと思います。
コロナ禍を通して、患者さんに寄り添う重要性が伝わりやすくなりました。例えば、新型コロナウイルス感染症にかかった患者さんは、よくわからない病気に対する不安と恐怖に襲われます。そんな時に、看護師が24時間あなたのそばにいて、寄り添い見守ってくれる。このような人としての尊厳が守られている感覚は治療にとって非常に重要です。これは看護師がやるべき、看護師にしかできない仕事だと思います。
── 「寄り添う」という言葉は、誰にでも使える響きがあります。しかし、実際には患者の尊厳を守るという仕事は、誰にでもできる仕事ではないわけですよね。
そうなんです。「寄り添う」は広すぎて、なかなか伝わりにくい言葉なんですね。例を挙げるならば、インシュリンの自己注射をしなければいけない人にコツを教えたり、きちんと自宅で接種できているかを生活状況と共に確認する。小さな赤ちゃんを失ったお母さんのそばにいて、同じ空間の中で気持ちを共有する。これらも全て、看護師に必要とされる「寄り添う」ことです。
また、一人ひとりの患者さんへ想像力を働かせる必要性もあります。例えば、カーテンの開け方ひとつでも、「この部屋の人は、昨日手術をした。痛みは治まったかな」といった情報を頭の中で思い起こしながらカーテンの開け方や病室への入り方を変える必要があります。
次のカーテンの中にいるのは、退院する患者さんです。そこでは多少明るく、カーテンをサッと開けてから、「おめでとうございます。今日は何時にお迎えに来られるんですか」という感じでお話をする。でも、病室のカーテンの先には、30分前に亡くなった患者さんとご家族がいるかもしれません。その時は、「おめでとう」の雰囲気を消して、ゆっくり深呼吸してから病室に入りカーテンを開けて入ります。
「カーテンを開ける」というひとつの所作でも、どんな人がいるかをイメージしながら、気持ちを推し量りながらかかわる必要があります。これが看護師に求められる「寄り添い」だと思います。

チームのマネジメントによる教育体制の確立
── 田中さんはJCHO中京病院でトップマネジャーとして、看護師向けの教育体制の確立に携わられていたとお聞きしました。今お話していた「寄り添い」を、病院の患者さん全体に行き届かせるために、どのような仕組みづくりをされていたのでしょうか。
ここから少し、管理職としての仕事の話をさせていただきますね。私が現在の職場に赴任してから、3年を期間として設定し、教育体制の確立・新人育成の仕組み化に取りかかりました。診療の補助技術の獲得や、マニュアルを刷新する仕組みの確立はそれほど難しくはありませんが、人材育成の仕組みを設計するのは難しいんです。
まず取り組んだのは、組織の看護のレベルと組織文化を把握することです。約3ヶ月ほど現状のリサーチに時間をかけた後、看護のあるべき姿を設定するためのチームを作り、キーマンとなるメンバーを選出します。そして、メンバーとは看護部組織の理念・方針を再構築するための議論を重ねて、仕事の習熟度に応じて段階的に細分化する 「キャリアラダー」を策定します。そして、キャリアラダーを審査する委員会を設立する。ここまでを新しい職場に赴任してから1年間かけて実施しました。
あとは、仕組みの定着化を図っていきます。キャリアラダー評価方法の指導、キャリアラダーにあった教育計画の策定、院内講師の選定、OJTに落とし込む工夫と看護師長教育を毎年続けることで、組織内に浸透させました。ここまでを、目標通り3年間で実施しました。
── 3年経過して、田中さんはその後どうされたのでしょうか。
キーマンとなるメンバーの責任者が、看護師全体を巻き込みながら仕事を進められていることを確認したら、3年を待たずして少しずつフェードアウトしていきます。持続可能な組織にするためには自分がいなくても機能するようにしておくのは重要なことだからです。
それまでは、作業を進めるうえで全ての工程に私自身がかかわることを徹底していました。メンバー個々の能力判定をし、能力にあった役割分担をして権限を委譲するところまで、惜しみなく力を注ぎます。しかし、最終的な目標は、私がいなくても看護部の組織が理念・方針に従って自走することです。人材育成は難しいですが、うまく波に乗ればこれほど楽しくやりがいのある仕事はないと思っていますね。

患者さんにとってより快適な病院を目指すために
── 病院設計と看護師のマネジメント、両面から患者さんに向き合われてきたと思うのですが、今後さらに看護師が改善できると思うポイントはありますか。
私たちはチームで医療を進める体制がベストだと考えていますが、患者さんの立場からすると、実はそれが弊害となっている可能性があると思います。
例えば、NST、緩和ケアチーム、認知症ケアチームなどさまざまなチームが一人の患者さんに関わると、治療や検査に関する同意書が何種類も発生します。すると、患者さんは外来や入院後1〜2日の間に複数の職種のスタッフと面会し、十数枚に及ぶ書類を渡され、書類を読んでサインをするということを余儀なくされます。
入院する患者さんの平均年齢は年々上昇し、80代や90代でも手術を受ける現代では、渡された書類はほとんど読まないまま家族がサインをしている、あるいは独居の方は読まないままサインをする現象が起こっています。また1日に多くのスタッフと会うため、主治医以外の顔は覚えていない状況です。
病院側からすると綿密な説明文を作り、チームで訪問し、手厚い医療を施しているつもりかもしれませんが、実際はご高齢の患者さんを混乱させています。そのため、今まで以上に看護師は患者さんのそばで支援者となり通訳となり、専門家の意見をわかりやすく伝える役割が重要になると思います。
また、看護師自身の働きやすさもまだまだ改善の余地があります。職場での人間関係と、自分がやりたいと思っているようなやりがいのある仕事ができているかどうかは、「働きやすさ」に大きく影響します。
病院では、スタッフが快適であれば、患者さんも間違いなく快適です。看護師が患者さんのために取り組めることは、まだまだ多く残されているのではないでしょうか。
Text by Tetsuhiro Ishida, Edit by Kotaro Okada